
第7話 三日月 crescent moon |
|
三日月には愛する想いを叶える力がある 中世から伝わる愛の魔術 嘘か誠か疑う輩は立ち去るがいい 信じるものだけが愛の願いを叶えられるのだ 疑うものはいつまでもそこで悩み苦しんでいればよい さあ 三日月の金曜日 卵の殻に小さな穴を開け、生卵を一気に飲み干せ 虚しい殻に愛しいひとの髪をひとすじ入れよ 穴を蜜蝋でできた赤い蝋を垂らして塞げ 紅で殻に色をつけよ 紅色の紐で殻を包むように結ぶのだ それをそなたの部屋に窓辺にそっと置け 三日月の夜 月光が静かにそれを照らすだろう ーーーさすれば幾つかの夜を越え そなたの想いが叶うだろうよ
イタリア マルケ地方に伝わる魔術より 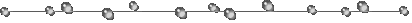 交渉相手と談笑しながら。 パソコンでメールを打ち終わったら。 会議中、社員の応酬を聞きながら。 真澄はふと、胸ポケットに手をあてる。 ここ数日で、そんなおかしな癖がついてしまった。 そこにある小さな紙片の存在を確認する。紙片は、もういい加減に皺が寄り、紙の感触も頼りなくなっているのに。そこに書いてある数字は、もう自分の携帯電話に登録してしまったのに。 けれども、実際にその番号を携帯電話に表示させたことはない。通話ボタンを押したこともない。 電波状態などと見え透いた嘘を言うのは何故なのか。 もう電話をかけたりしないなどと言うのは何故なのか。 導き出される答えは、ひとつしか無い、と思う。 “会いたい”などと、愚かな戯言を言ってしまったから。 その声に真実を感じてしまったから。 そして、そこで紫織の声が届いてしまったから。 特別に好きでもない男に“会いたい”などと言われて喜ぶ女はいない。それを男の妻に聞かれて、泥沼に好き好んで嵌る女もいないだろう。 だがそこで、もう一つの疑問に出会う。 では、毎晩電話を掛けてきたのは何故なのか。 楽しげに。この場所だけに。非通知で。 一方通行の繋がりを続けたのは何故なのか。 何故なのか。何故なのか。何故なのか。 疑問符ばかりが、虚しくいつまでも巡る。 パズルのピースは規格外ばかりだ。 答えは、遥か遠いところにあるのだろうか。案外、すぐ傍にあるのだろうか。小さなきっかけでいい。規格外のパズルを解く鍵が欲しい。 この手の中にマヤへ繋がる番号がある。 今、確かなのはそれだけだ。 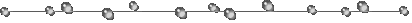 もう電話をかけたりしない、という言葉通り、マヤからの連絡は一切途絶えた。今までもーーマヤに出会ってからーー顔を見ずに、声を聞かずに何日も何ヶ月も過ごしたこともある。それでも、過ごしてこられていたというのに、今はだた焦燥感ばかりが募る。 蜘蛛の糸のような儚い繋がりは、とうに切れてしまっているのではないか。何もかもが終わってしまっているのではないか…。 それは、恐怖にも似た感覚だ。 真澄は大都芸能の売り出した新人アーティストの出演番組をチェックするため、社長室のプラズマテレビをつける。一旦書類の扱いを中断してソファに身を沈め、煙草に火を付けた。 煙を長く吐き出すと、また何気なく胸ポケットに手をあててしまう。 そこに紙片は確かにある。ひどく頼りなく。 テレビからは賑やかしく空騒ぎの映像が流れている。新人はそれなりにピックアップされた扱われ方をしており、それに大方満足する。新人の出演場面が終わり、画面はCMに切り替わった。もう見る必要もないとリモコンに手を伸ばし、真澄が目線を画面から逸らそうとした、その時。 視界の端から否応なく入ってくる映像。 画面は一瞬真っ暗な闇の中に包まれる 底辺には女性ヴォーカルの痺れるようなアカペラ 柔らかな光に包まれて揺れる月の船 薄衣をたおやかに纏い 黒髪を緩やかな風になびかせる女性 それは白い月の精 月の精は裸足で地にそっと降り立ち 小走りで駆け寄る 花びらがこぼれるように 愛を込めて ほほえむ 手にはカクテル くちびるは キス このくちびるに伝えてよ 恋ごころ 甘く酔うほどに 白い肌に流れる黒髪。 恋に潤んで煌めく大きな瞳。 グラスが触れる艶やかな唇。 カクテルが喉を通り、甘い溜息を零す。 それは酒造会社のカクテルのCM。 だが、真澄にとってそれは、ただのCMでは終わらない。大画面から圧倒的な存在感で、訴えかけてくる、その月の精はーーー マヤ。 足下から甘い痺れが湧き上がり一気に全身を支配する。 胸が異様にざわめき、視線を外すことなどできない。 わずか数十秒の映像に魂を奪われ、言葉を失う。 マヤが、いた。 映像の向こうで、微笑んで、恋に潤んで。 消えゆくのかと思えば、また思わぬところから現れる。 森羅万象の源は、今夜、月の精となり微笑みかける。 そうなのだ。 マヤは消えない。 マヤは自分の中から消えたりはしない。 マヤを永遠に失わない。 姿を変え、仕草を変え、微笑み方を変えたとしても その影は一生、目の前を惑わすように揺らめいていく。 ーーーー恋ごころ 甘く酔うほどに マヤ。 腹の底から笑いが込み上げてくる。 そうだ、マヤ。 いくらでも、いつまでも、君にならば語りかけることができる。 偽りない、心からの想いを。 あの瞳は、俺だけのものだ。 マヤは、あの瞳は、 この部屋にいる、この俺に向けて訴えているんだな。 全てのピースがまるで魔法が掛かったかのように、 ひとりでに動き出し、ぴたりと自分の居場所に嵌りだす。 それが、全ての疑問符の答えにならないか? 今、思うこの考えは間違えているか? 狂っているか? ひとりよがりの恋に溺れた愚かな自己満足か? 笑いが止まらない。 狂っていて結構だ。 愛することは、狂気の始まりだ。 すべては錯覚で幻だ。 錯覚ならば、思うように生きて何が悪い。 思うように生きることが過ちと言うのなら、 縛り付けられながら偽りを生きることも取り返しの付かない過ちだ。 堕ちてしまえばいい。煌めく欠片ともに。 堕ちた先には、たった一人、マヤだけがいればいい。 自分を縛り付けるあらゆるものを、 解いていくことを、もう厭わない。 マヤと永遠に繋がっていくことができるのならば。 「社長…?お出かけでしょうか?」 背広を着てコートを持ち社長室から現れた真澄に、水城が驚きの声を上げる。まだ夜を迎えたばかりで、今夜もいつものように深夜まで仕事漬けの予定だった筈だ。 「いや、今夜はお開きだ。君も今日は帰っていいぞ」 「…そう、おっしゃいましても…」 戸惑う水城に、真澄が笑う。 「おそらく、これから君に、今以上に迷惑をかけることになる。だから、今のうちに帰れる時は帰っておいた方がいい」 迷いのないその笑いに、水城は息を呑み、眼鏡の奥から真澄を凝視する。 「君が俺に愛想を尽かさなければの話だが。なにしろ気付くのも、行動を起こすのも、全てが遅すぎるからな。きっと有り得ないほどの事態になる」 真澄が何に気付き、何を起こすのか。 言わなくても水城にはわかる。 影を背負い、しがらみに縛られてきた憑き物が落ち、変わりに普段から真澄を見慣れている筈の水城さえ、はっとするほどの切れと色気を纏った真澄の姿。 「お覚悟の上ですのね」 「ああ。だが、本来ならば、立場上、これからのことを考えて手を打ってから行くべきだと思うが、すまないが、今はこのまま行きたいと思っている」 とうとうこの日が来たかと水城は思う。 遠い日、何事にも冷静な目を向けていた真澄の内に、密かに潜む強い想いに気付いた時から、このままでは終わらないと思っていた。むしろ、このままで終わらせて欲しくはなかった。 尊敬して、愛すべき、困った上司に、水城は肩を竦めて笑みを返すと、深々と一礼する。 「いってらっしゃいませ。…それから、今後とも宜しくお願いいたします。思う存分なさいませ」 「…君は最高の秘書だな」 秘書の心遣いに深く感謝し、真澄はエレベータの下ボタンを押す。 堕ちるために。 恋しい人のもとへ急ぐために。 狂うほどの愛しさを抱えて男は向かう。 三日月の夜に 迷い無く。覚悟を決めて。 01.31.2005 |
| index next |