
第6話 新月 new moon |
|
今夜は寒いな。 そう思ったから、お鍋に水をたっぷりと入れて強火でがんがんと湧かしている。これからこの鍋にうどんを入れて茹でるつもりだ。本当はもっと大きな鍋の方が零さずに茹でやすいけれど、でもこれしかないから、これでやってみる。 とにかく。マヤはざくざくと葱を刻みながら思う。とにかく、ひとりでちゃんと生きていかなくてはいけないのだから、自分で食べるものぐらい用意しなくちゃいけない。チョコだけ食べて生きていくわけにはいかない。麗はずいぶん心配していたけれど、もういい大人だから一人で自分のことぐらいやるから、と笑ってみせた。まな板の上に散らばった刻んだ葱を小皿に移して、一人分の乾麺を握る。 大都芸能以外の事務所に所属するつもりなど毛頭なかった。けれど、だからといって大都芸能に入るのは抵抗があった。もちろん、大都芸能に恨みがあるとか、そういうことではなく、真澄の大都芸能に入ることに抵抗があった。 大都芸能に入る。真澄の取り扱う商品になる。 それは、自分の望んでいる事じゃない。 商品にはなりたくない。 一人の人間として、女性として、真澄と対峙したい。 …そんなことができるはずもなく、人間として対峙できたとしても、女性として対峙できる場面はもう、ない。 そもそも、自分は真澄に女性として見られたことなんて一度もない。 だけど、莫迦かもしれないけれど、それでも、“真澄の商品”にはなりたくなかった。 大都芸能からの誘いを断ったのは、たったそれだけの理由。周りの人は、大都芸能にはいろいろとあったからね、と深く追求はしてこなかった。 でも紅天女は真澄の手によって上演してほしかった。あれほどまでに紅天女に拘ってきた真澄に、紫のバラの人として自分を支えてきてくれた真澄に、自分の紅天女を贈りたかった。そして、一緒に紅天女を創っていきたかった。 これ以上の私情はないと思う。 矛盾してると自分でも自覚している。ちぐはぐ。 自分の中に渦巻くいろいろな想いは、理路整然と整理したくても全然できなくて、いつもあやふやに揺れている。だから、ほとんど直感で決めた。 フリーで活動することも。 上演のプロデュースだけの契約をすることも。 ちぐはぐな自分らしい、と思う。 だしは、ちゃんとかつお節でとった方が美味しいんだよ、と麗が言っていたから、見よう見まねでやってみた。…だしを取り終わったかつお節は用済みで捨てちゃうのかな。よくわからない。今度会ったら聞いてみよう。お醤油とお酒の分量は絶対失敗しそうだから、売っていたつゆの本を使ってしまう。次こそ、自分で配合するから。 鍋の中でうどんが泡にまみれて下から上へぐるぐると巡っている。ひとりの部屋には、お湯の沸き立つ音とガス台の炎の音が静かに一定の調子で流れている。どのくらい茹でればいいのだろう。菜箸でうどんを突いてみる。うどんの入っていた袋には、お好みの固さになったら、と書いてある。お好みの固さが、どのくらいだか分からないから読んでいるのに。 うどんを一本箸でつまんで、ふうふうと息で冷ましてから口に入れてみる。こんなもんだろうか。麗はいつもどのくらい茹でていたんだろう。 一人分の引っ越しの荷物は驚くほど少なくて、衣類と少しの雑貨と台本、アクセサリーも靴も必要な物しかなくて、いくつかの段ボール箱を眺めて、自分という人間はたったこれだけの荷物があれば生きていけるのだと、そう思って、なんとなく気が楽になった。 この引っ越しは最初の一歩。 自分が歩いていくための最初の一歩。 引っ越し荷物の中の、一つの段ボール箱。 ひときわ大事に扱う箱には、紫のバラの人からのプレゼントが入っている。この箱はもう開かないと決めた。 真澄への想いと共に、この箱の中入れておく。 箱の中に入れておくというのは 決して捨て去るということではなく 忘れ去るということでもなく 大切にしまっておくということ。失うわけじゃない。 大切に。いつまでも。 卵なんて入れたら、月見うどんだよ。 葱を散らしたら、おぼろ月夜みたい。 なんとか完成したうどんを、ひとりの部屋でずるずるとすする。 熱いよ。 食べながら、鼻の奥がつんと痛くなって、なぜだか泣けてくる。 ぽろっと涙がこぼれた。こぼれるままに。 鼻をすすって、それでも食べ続ける。 「…おいしー……」 ほら、おいしいもん。やればできるんだもん。 ずる…ずる… ちゃんと。 ちゃんと一人でがんばれる自分になる。 紫のバラの人がいなくても、速水さんがいなくても がんばれるようになるから。 これを食べ終わったら、体がぽかぽかに温まったら電話をしよう。 この前は突然電話切ちゃってごめんなさい。電波状態が悪かったのかな。それに、いろいろとばたばたしてて、お詫びの電話もできなくてごめんなさい。その後、元気にしてますか? “謝る”という行為は、相手を思いやると同時に、自分の心の負担を軽くするための行為でもあって、確かにその通りで、鉛のような心をほんの少しだけ軽くしてもらったら、あとは、もう、がんばろうと決めた。 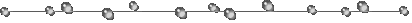 ロンドン支局と連絡を取り合いながらの打ち合わせを終えて社長室に戻ると、申し分のないタイミングで水城がコーヒーを運んできた。あと数分で日付が変わる。 「お疲れさまでした。ずいぶんと揉めたようですわね」 「…ああ、向こうは言いたい放題だ。まあ、その要望を調整するのもこちらサイドの役割だからな…」 執務机に凭れて苦笑しながら、コーヒーを一口含む。 疲労感がじわりと押し寄せてくる。 「君も遅くまで残ってもらって、すまなかったな」 「いえ…、明日の資料の準備もございましたので」 「ーーそれから」 水城が含みを持たせながら、話を続ける。 無表情ながら、眼鏡の奥で瞳が何事か語っている。 こういう時は居心地の良い話をされた試しがない。 「なんだ?」 コーヒーの濃い色が天井の照明を映している。 「先ほど、社長室にマヤちゃんからお電話がありました」 どくりと心臓が波打つ。 ーーーマヤちゃんからお電話が 手のなかのコーヒーが揺れる。 「チビちゃんから…?」 「はい。…何か要領を得ない話しぶりでしたけれど、…あの子らしいですわね。要約すると、先日こちらにお電話した際に、突然切ってしまって申し訳なかった、電波状態が悪くて、と、そういうことらしいのですが、お心当たりなどございますか?」 「……ああ…」 電波状態…か。 そういうことにしたのか。 まだ、何か言いたげな水城に視線を投げる。 「それで、もう電話をかけたりしないので、安心してください。おしゃべりに付き合ってもらえて楽しかったです…だそうですわ」 ーーーもう電話をかけたりしないので 消えてしまう。 手の届かないところへ。 追いかけることさえ、拒むように。 「実はマヤちゃん、最近転居なさいまして、まだ新しいマンションにはお電話を引かれていないそうなのですわ。それで、先日、転居の連絡を私がいただいた際に、契約のこともございますし、こちらからの連絡先を伺っておりましたの」 水城の真っ直ぐな黒髪が揺れる。 「携帯電話の番号でございますけれど」 濃い色の中の照明が、ゆっくりと弧を描くように揺れる。 揺れている。 「一応、大都芸能として伺った番号ですので、社長がご存じでも差し支えないかと。もし、先ほどの件で折り返しのお電話をなさるのでしたら…」 そう言って、水城は小さなメモ用紙を真澄の目の前に差し出す。 090から始まる11桁。 この数字の向こうに、マヤが、いる。 夜空に浮かぶのは、 生まれたばかりの蜘蛛の糸ような 新しい、細い、月。 01.30.2005 |
| index next |