
第5話 晦月 dark moon |
|
朝の光を受けながら、真澄は少しばかりのクロワッサンをコーヒーで流し込む。紫織はやや俯き加減でテーブルの向かいに座り、右手に柔らかな湯気が漂う紅茶茶碗を、左手にソーサーを持つ。結婚して紫織が速水の屋敷に住み始めて以来、ほぼ毎日繰り返される光景。夫婦が揃う朝のひととき。 “…お仕事中…申し訳ありません…。 ただ、今夜はもう少しおそばにいたかったのですわ…” あの夜、受話器を置いた真澄に紫織はそう言った。真澄が思わぬ事を言い始めることを恐れるように、謝る必要など何もないのに言い訳めいた言葉を述べた。 手指を固く握り締めながらも、口元は懸命に笑っていた。 真澄がマヤの名前を呼んだことも、会いたいと言ったことも間違いなく耳に届いていた筈だ。けれども紫織はそれに一言も触れない。 ただ、もう少しおそばに…と。 紫織が冷静を装えば装うほど、真澄も言葉少なになる。例えば、そのことについて問われたのなら、仕事の電話だったのですよと嘘の言い訳をすることもできる。決定的な言葉は何も言っていないのだから。だが、紫織が触れないことで、あの夜真澄がマヤに放った言葉は、真澄と紫織の間では存在しないものになった。例え心の中でいつまでも蠢いていたとしても。 真澄がコーヒーカップを置き静かに立ち上がる。紫織がそれにつられるように顔を上げる。紅茶茶碗を置き真澄の後に続く。紫織の持つ背広に腕を通し身支度を整える。“では”といつものように口の両端を持ち上げて言うと、紫織は“お帰りは?”といつものように問いかける。玄関で靴ベラを持ち革靴を履きながら“今夜も遅くなるでしょうね。先に休んでいてください”といつものように答え、光溢れる外に出る。“いってらっしゃいませ…”紫織は真澄が迎えの車に乗り走り去るまで見送る。ほぼ毎日繰り返される光景。すれ違う心の奥を見透かしながら、それでも繰り返されていく光景。 いつものように。いつものように。 もっとうまくやれると思っていた。寄せられる愛情へは誠実な気持ちで応じられると思っていた。狂うほどに叶わぬ想いは、歪ませながらも無理に封じ込めてしまえば、いつか諦めに変化していき、やがて記憶の中だけに存在するものになるのだと思っていた。 微笑んで朝の言葉を交わす、一日を語り合いながら夕食を共にする、時には花を買って帰る、夜には抱き寄せて囁き合い体温を感じながら共に眠る。やがて紫織の笑顔を自分も喜ぶようになり、共に生きていけると思っていた。そうするべきなのだと思った。一生。 ーーーー甘すぎる。 自分を愛していない女ならば、いくらでも抱ける。心を感じない男と女として、どんな愛の言葉も操れる。体を絡め合うこともできる。 紫織が政略結婚だと割り切った考えだったのなら、或いは抱けたかも知れない。紫織が自分に愛情を持っていなければ、或いは逆にうまくいくのかもしれない。だが現実は違う。それぞれが得られないものを求めている。 マヤ。求める相手はマヤだけで、求めるものはマヤとマヤの心。 朝の言葉を交わしたいのも、抱き寄せて囁き合い体温を感じながら共に眠りたいのも、ーーーそれはマヤだけだ。 溜息をつく。 救いようのないほど心を支配している想いは、封じ込めることなど到底無理な話だったと今更ながらに深く自覚する。儚くも繋がってしまった時間は、無かったことにはできない。したくない。 ではどうする。 待つだけか。出来ることは待つだけか。 マヤには一度も聞いたことはない。 どんなつもりで電話を掛けてくるのかと。 どんな想いを込めて、 決まった時刻に決まった時間だけ自分と繋がるのかと。 蜘蛛の糸が切れることだけを恐れて 聞けないままでいる。 真澄を乗せた車が赤信号で停車する。 冬の朝の街並みは、どこかよそよそしく清冽としている。 愚かな迷いを抱えている自分には、およそ相応しくない時間。 マヤはどうしているだろうか。 突然途切れた通話。 あれ以来、深夜の社長室の電話は呼び出し音を鳴らさない。 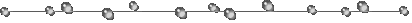 思いがけないことを耳にしたのは、その日の夜だった。 事業部長と経理担当取締役との応酬でずいぶんと長引いた会議に、真澄が経営判断で決着を付けようやく席を立つ。経理側の言い分は充分承知の上だが、今は攻めの姿勢を崩すときではない。経理側にはいずれ別件でフォローを入れよう。水城に数件の指示を出しながら会議室から社長室に戻る廊下で携帯電話が震えたのに気付いた。液晶画面でそれが聖であることを確認すると、電話はいつも通り一旦切れた。真澄は社長室に入り扉を閉じて掛け直す。 「俺だ」 「ご連絡ありがとうございます。先日ご依頼のありました件、調査結果が出ましたのでご報告を」 「ああ、三ツ木出版の件だな」 「はい」 聖は幾つかの極秘事項についての報告を手短に行う。そして真澄の労いの言葉を聞くと、一拍の間をおき、マヤさまのことですが、と切り出した。 「マヤの?」 聖の口からマヤの話が出るのは珍しいことではない。マヤは「つきかげ」所属だとはいえ、事実上フリーで活動している。力ある事務所に守られている状態とは異なり、トラブルにも巻き込まれやすい。聖には、マヤの動向を密やかに見守るように指示してあった。 マヤから社長室への電話が無くなってから、もう10日以上の時が経っていた。初めての電話以来二日と空いたことはなかったのに。マヤに何かトラブルでも発生したのだろうか。さりげなさを装ったつもりだが、言葉に力が籠もってしまったのは聖に伝わってしまっただろうか。 「はい。最近マヤさまとはご連絡を取られていらっしゃいますか?」 返事の言葉が鈍る。聖はマヤからの毎晩の電話を知らない。そして、その電話が途絶えていることも知らない。 「…いや」 「…さようでございますか。では、3日前にマヤさまが転居なさったのはご存じでしょうか」 「転居?引っ越したのか?あのアパートから」 「はい。小さなマンションを借りられてお引っ越しなさいました」 「青木君と一緒か?」 「青木さまもあのアパートを引き払ったようですが、青木さまとは別のマンションでした。青木さまが借りたマンションとはごく近い場所ですが」 「完全な一人暮らしというわけか」 「そのようでございます」 「…そうか」 「…理由までは存じ上げませんが、紅天女になられてお仕事も増え収入もある程度安定していらっしゃったようですので、特に深い意味は無いかとは思いますが、念のため」 「わかった。…承知しておこう」 聖から簡単に場所を確認して電話を切り、窓の外を眺める。 月が欠けても、星が見えなくても、 眼下には煌びやかな人工の星が溢れている。 偽りの光が夜空に膜を作り、天に瞬く真実の星光は地上に届かない。 光が川のごとく流れる渋滞の首都高。 天辺で紅い光が不規則に点滅する高層ビル群。 人の営みの確かな証である暖かな光の粒。 マヤが自分の場所を移した。あたらしい場所へ行ってしまった。 そうだな、別に特別なことではない。マンションの場所も以前のアパートからそう遠くない。確かに危なっかしい限りだが、なんとか仕事の契約を周りの人間に助けてもらいながらも自分で行い、ドラマや映画の仕事もこなし始めている。警備上の問題もあるし、あのアパートよりはマンションの方がいいだろう。 聖の話を咀嚼しようと、とりとめもなく考えが巡る。 “お久しぶりです…。速水社長、奥様” パーティで出会ったマヤの姿を思い出す。 自分の知らないマヤ。 前のアパートの連絡先なら掛けることは無くても知っていた。紅天女の契約のこともあるのだから、おそらく水城にはマヤから連絡が入るだろう。水城に聞けばすぐにも新しい連絡先が分かるだろう。新しいマンションの電話番号も携帯電話の番号も調べようと思えば、すぐに調べは着くだろう。 “……いえ、やめときます。社長室の番号だけ知ってれば…それでいいです…。 …それも…やめときます…。あたしから…今度社長室に電話します…から…” だが、マヤがそれを望んでいない。 マヤは自分からの連絡を待ってはいない。 夜空には 闇に呑まれる月が 儚く消え去る前に最後の光を細く放っている。 マヤが。 消えてしまう。 闇の中へ、振り向かずに。 01.27.2005 |
| index next |