
第4話 鎮静の月 balsamic moon |
|
通話を切断すると、 携帯電話を抱きかかえるようにマヤはその場にしゃがみ込む。 微かな震えが止まらない。 “あなた…” あれは紫織の声だった。 真澄だけが繋がる筈の電話の向こうのその奥から ーーーー紫織の声が聞こえた。 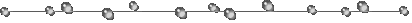 大都芸能社長室の直通の電話番号は、大都と交わした契約書類に書いてあった。大都側担当部署名と担当者名、連絡先電話番号の印字された文字の下に、ボールペンで社長室直通番号と走り書きの文字と数字の羅列があった。おそらく契約に事実上携わった水城が便宜の為に書いた文字なのだろうと思う。 その数字の羅列を見つけたマヤの動きが止まる。 それから、そこを指で何度もなぞる。 この番号の向こうに速水さんがいる。 そう思うだけで泣けてしまいそうだった。 何度も思い描いた真澄の姿はマヤの心の中の一番大事なところにあって、いつでも鮮明に思い出すことができる。小さく笑った口元や、勝ち誇った視線や、思いがけず見せてくれる穏やかな眼差し、煙草を挟む長い指、煙を吐き出す時に顔を背ける顎の線、広い肩幅。 それから耳の奥で今も優しく漂うあの声。 “おめでとう、マヤ。 君の紅天女と出会えて…たぶん俺は誰よりも幸せだ” 噛み締めるような低音で穏やかな声。 マヤの許に紅天女が降りた夜、真澄は確かにそう微笑んで祝福してくれた。一瞬、紫のバラの人として言ってくれたのではないかと、そう錯覚するほど、優しい気持ちの籠もった声だった。速水真澄として目の前に来て、紫のバラの人としての心を伝えてくれたような、そんな声だった。 マヤ。おめでとう、マヤ。名前を呼んでくれる真澄の声。 それはこんなにも自分を癒して どうしようもないほど胸を痛ませる。 見つけてしまったその電話番号をマヤはしばらく迷った後、携帯電話のアドレスに保存した。違う。電話をかけるために保存したんじゃない。ただお守りにしようと思っただけ。そう自分に言い聞かせる。時々、携帯を開きその電話番号を眺めて黙って携帯を閉じる。本当にそれだけだった。 マヤと紅天女に関する契約を締結すると、真澄は何一つ滞りなく予定通りに紫織と結婚した。誰もが真澄のことを紅天女と実りある美しい妻を手に入れた幸せ者だと言い、マヤの目にも紫織の隣にいる真澄は幸福そのものに見えた。 手の届かない人になってしまった…。 そう思った直後、可笑しくなる。 じゃあ、今までは手が届いていたのか? そんなことはない。 最初から手の届かない人だったじゃないか。手の届くはずのない人を好きになって想い続けて傷ついて痛がっている。 正気じゃないと思う。結婚した人をいつまでも未練たっぷりに想い続けているのは潔くないと思う。そんなことは分かってる。 そう思う冷静さはまだ自分の中にある。 だけど。 好きになるのに、正しいも間違えもない。選んで好きになっているわけじゃないのだから。好きになってしまったんだから。 どうして好きになったのか、なんてどうでもいい。紫のバラの人だったから…とか、見守ってくれた優しさに気付いたから…とか、そんなのはみんな後から考えて付けた理由で。そうじゃなくて。 ただ、いつのまにかその存在がそこにいるだけで泣けそうなほどに幸せで、その存在はかけがえのないもので、絶対的なもので…。 切れ長の微笑んだ瞳が脳裏に浮かんで堪らない。 あの夜は大きな満月で、マヤは月光に導かれるようにコートを羽織るとふらりと外に出て行く。行くあてが有るわけではなく、ゆっくりと月明かりを浴びながら月の見える道を選んで歩いた。夜は優しい。強がりも弱さもみんな月の光が優しく許してくれる気がする。突き抜けた青空よりも今は穏やかな冷たさの夜がいい。 見知らぬ公園の砂場の縁に腰掛ける。 昼間小さな子供が作ったのだろう崩れかけた砂の山と忘れられた黄色いプラスチックのシャベル。風がざわりと吹いて枯れ葉が絡まるように目の前を通り過ぎる。コートのポケットの中で握り締める白い携帯電話。手の中で何度か回転させる。満月の光が柔らかくマヤを包む。 …かけてみようか… ふと。今まで思っても即座に否定してきた考えが頭をよぎる。 声が聞きたい。 電話が繋がったらなんて言われるだろう。迷惑そうな声を出すのだろうか。冷たくあしらわれるだろうか。からかわれて終わるのだろうか。そもそもどんな用件があるというのか。何を話すつもりなのか。 ご結婚おめでとうございます。今、幸せですか?とでも…まさか。 携帯電話をポケットから取り出し、社長室直通番号を呼び出してみる。闇に浮かぶ液晶画面に03から始まる10桁の数字。ただの数字だけれど、これは真澄に繋がる数字で、右手の親指で通話のボタンを押してしまえば、あの部屋の電話が真澄を呼び出してしまう呪文のような数字で。 おめでとう、マヤ。 声が聞きたい。真澄の声を。たった一言でいいから。 体中の血流の圧力がすべて右手の親指に集中するようだった。 震える指が通話のボタンを押した。 一瞬の沈黙の後、心臓の鼓動をさらに早めるような呼び出し音が確かに電話の中から聞こえてくる。 それでも、その音を耳に当てながら次々と考える。時間はもう11時を過ぎている。声は聞きたいけれど、でもたぶん出ない。いくら仕事が忙しい真澄でも、もう紫織の待つ家に帰っている時間だろう。結婚したばかりの幸せな二人なんだから。幸せな二人なんだから。 プツ…。呼び出し音が途切れた。 “はい。…速水です” 機械を通したやや籠もった声。 それは紛れもなく真澄の声で、 ずっとずっと耳の奥で漂っていた真澄の声で、 マヤは頭の中が真っ白になる。 速水さん…。 喉の奥が締め付けられるように痛み、言葉が出ない。 名乗れないまま沈黙していたのに、真澄にはわかってしまった。こんな夜中に馬鹿な電話をかけるのは、今も昔も自分ぐらいなのだ。 けれども、それが死ぬほど嬉しい。真澄が受ける何人もの電話の相手の中から、たった一人自分を言い当てられたことが死ぬほど嬉しい。本当は、それがただの偶然だったとしても。 もっと冷たくあしらわれると思ったのに、“…風邪…ひくなよ”なんて、“気を付けて帰るんだぞ…”なんて言うから、堪らなくなってしまう。そんなことを言われたら、どのくらい心が騒ぎだすか知らないから真澄は平気で何でもない事のように言う。 受話器から流れる真澄の声は真っ直ぐにマヤに届く。どこにもぶつからずに心の芯に真っ直ぐに。優しく穏やかで少し哀しい会話。現実感のない時間に、マヤは思わず言ってしまう。 “夜……時々…電話しても、いいですか…?” 神様が許してくれなくても世界中で真澄だけが許してくれるのなら、毎日真澄に流れる時間のほんの少しを自分と繋がる時間にして欲しいと思った。贅沢な願い。電話だけでいいから繋がることを許してください。そう祈りながらマヤは言ってしまう。 マヤの意味不明な願いを真澄はいとも簡単に叶えてしまう。気分転換になるからだと、ごく気軽に。 ああそうなのだ、と我に返る。 真澄にとって自分はそういう存在なのだ。 真澄の人生という本流には決して関われない。与えられる役割は本流から外れた場所。そういえば、昔から言われていた。君といると飽きないなと。それならば、その役を完璧に演じて見せよう。女優なんだから。できない役など無いのだから。 心の何処かから、そんな役割を演じることは不毛だと声が聞こえる。わかっているけれど、今はこの場所が必要だった。繋がっていられる時間が欲しかった。世の中の誰から見ても実りのない役割だとしても。誰に分かってもらえなくても。 だから決めた。紫織のいる場所には電話しない。掛ける番号は社長室直通だけ。決して携帯電話の番号は聞かない。聞けば絶対に掛けたくなってしまうから。 真澄からの電話を待ってしまうこともしない。電話をかけるのは自分から。自分の携帯電話の番号も教えない。携帯電話の番号を教えてしまったら、おそらく毎日愚かなほど携帯電話が震えるのを待ってしまうから。 真澄の負担にならないために長電話もしない。ずるずると繋がる時間を一秒でも長く伸ばしたくなっても潔く切る。役割をいつまでも演じたければ、潔く。 役の解釈のために決めた決まり事を、マヤは忠実に守った。けれど。 “あなた…” 社長室に紫織がいた。 “この時間に電話をくれるのは君だけだと俺の中で決めている” そう言ってくれたことがあった。深夜の社長室の真澄は、繋がっていい真澄だと思っていた。けれど、現実にはこの真澄にも紫織はいる。 真澄の言葉は霞のようだ。手を伸ばしても強く掴んでも、手のひらには何も残らない。ただ、自分の爪の痕が手のひらに紅く滲むだけ。 ーーーー会いたい。 なんて魅惑的で哀しい言葉なんだろう。 会いたい。会いたい。会いたい。 一つの言葉に込められている湿度も温度も密度も、自分が発するものと真澄のものでは、きっと雲泥の差がある。その計り知れない差を埋める術は見つからない。 会いたい。息が止まるかと思うほどのその言葉は 同じぐらいの寂しさを連れてくる。 真澄との会話は嬉しくて哀しい。 白い携帯電話を抱き締めて 夜の中にしゃがみ込んだまま、マヤは動けない。 いつまでもこの場所にはいられない。 この場所に慣れてしまってはいけない。 満ちていた月は、ゆっくりと姿を変え確実に欠けていく。 やがて月光も届かない 闇が包むだけの夜に近づいていく。 01.25.2005 |
| index next |