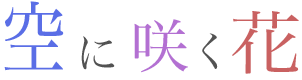
|
|
速水さんの異変に気が付いたのは、たぶんあたしが一番最初だったと思う。その証拠に水城さんは当然のように今日一日の予定を報告していたし(午後は会議が三つもかけ持ちで入っていた)、その後に社長室に入ってきた音楽部門の取締役という少し白髪の交じった男の人も、なんだか緊張した面持ちでCDの売り上げについて報告をしていた。最近はメガヒットがなかなか登場しないから苦戦が強いられているけれど、案外クラッシック系のCDが静かに売れているのだと、その人は汗を拭き拭き一生懸命に説明していた。仕事中は余計な発言はせず、若干不機嫌な顔をしながら必要なことだけ手短に指示する速水さんのことだから、その変化はわかりにくかったのだろうと思う。 そもそも何故あたしがここにいるかと言うと、今日の朝一番で社長室に来るようにと指示がマネージャーを通してあったからで、たぶん話の内容というのは今度発売になる週刊誌に撮られてしまった写真のことだと思う。 その写真というのは、いわゆる熱愛スクープというやつで、あたしがドラマで共演した俳優さん(相楽くんと言って、あたしより一つ年下のなかなかいい男ではある)と一緒に夕食をとってレストランを出たところ、お酒を飲ませてくれる店までいくところ、最後にあたしのマンションまでタクシーで送ってくれたところをバシバシ撮られてしまったのだ。別にキスしたところを撮られたわけじゃない(してないし)。相楽君は送っただけで乗ってきたタクシーでそのまま帰って行ったけれど、写真と一緒に載っている記事を読むと、いかにも熱愛中カップルに見えてくるから不思議だ。 速水さんは、これについて事実の確認をしようというのだろう。そんなの電話で済む話なのに、速水さんはなにかと理由をつけてあたしをここに呼び出す。 それは、あたしが速水さんのお気に入りの女優だからだ。大都芸能に所属しているたくさんの俳優、タレント、歌手、その中でもとびきりのお気に入りだ。なんといっても紅天女なわけだし、その昔、紫のバラを匿名で贈っていてくれたぐらいだし。 お気に入りの女優。なんとも、つまらない役回りだ。 「待たせたな」 そういって速水さんは目の前のソファに座るけれど、やっぱりおかしい。誰も気が付かないのだろうか。というか、本人すら気づいていないようだけど。 「これなんだが、…いつもの話か?」 写真のページを広げながら目の前に週刊誌を差し出す。あたしは黙って頷いて、さらにニコリと笑ってみせる。 「もちろん。だって途中までほかの女優さんも一緒にいたし、そんなんじゃないですよ」 「…そうか。なら、いい。ドラマの宣伝にもなるからな。ただ、君の価値が落ちるような男とは撮られるなよ」 「はーい」 元気に返事をしてみせると、涼しい目でちょっと笑った。 それだけだ、と言って立ち上がろうとした速水さんが、突然、膝から倒れた。 「速水さん!」 慌てて駆け寄ると額に脂汗が滲んでいた。ためらわずに手を握る。やっぱりすごく熱い。どうしてこんなに熱があるのに平気な顔して仕事なんてしてるんだろう。すぐに水城さんを呼ぶ。 「まあ社長…、かなりの高熱ですわよ。今日はもうお帰りになった方が…」 「…少し怠いと思ってはいたが…。しかし、今日は先方を招いての会議も入っていただろう。あれを欠席するわけにはいかない…」 「その時間帯でしたら副社長の予定が空いておりますから、代わっていただけますわ。このところ、いつもに増してのハードスケジュールでしたもの。お疲れもたまっていらっしゃるはずですし、とにかく本日はお休みくださいませ」 「…そう…か…」 有無を言わせない水城さんの勢いに反論する力もないらしい。ソファに体を預けてぐったりしている。 「…でも、お一人で帰すには、ちょっと心配なご様子ですわね」 水城さんが思案顔になっている。そんなの、速水さんのお屋敷に一言告げれば速効お迎えの車が来て、帰れば綺麗な奥さんが優しく看病してくれる楽しい結婚一年目なのに、何を言っているんだろう。 水城さんが突然振り向き、あたしと視線を合わせる。 「そうだわ、マヤちゃん。今日はもうオフだったわよね。もう撮影もクランクアップしたはずよね」 「ええ、まあ」 今日はこれから夏用の花の飾りの付いたサンダルを買いに行って、その後、映画を観に行く予定が入っている。一人でだけど。大作は撮らないけれど、面白い優しい映画を作る大好きな監督の作品を、銀座の小さな映画館に観に行くつもりなのだ。 「悪いけど、社長を送っていってくれるかしら…?」 …それは、ごめんこうむりたい。あたしは、あの綺麗な奥さんがちょっと苦手。あの人に会うのは極力避けたい。 「一人で大丈夫だ。…部屋に帰って薬飲んで、おとなしく寝てるから」 あたしが返事に困っていると、速水さんが目を瞑りながらそう言った。 「社長、マンションのお部屋にお薬はございますの?」 「…さあ、どうだったかな」 弱く笑いながら速水さんが答える。なんだか変。話が変。 訝しげな顔をしているあたしに、水城さんが気が付いた。 「ああ…。社長は今、お一人でお住まいなのよ。だから、途中でお薬買って、お部屋まで送り届けてほしいんだけど…。私ができればいいのだけれど、いろいろ調整しなきゃいけないし、ちょっとここを離れられないのよ」 「はあ…」 お一人でお住まい…って、なんなのか。水城さんは所属の女優というよりは、昔からの知り合いにお願いする面持ちで懇願している。だから、昔からの知り合いということで、引き受けてしまった。綺麗な奥さんにも会わなくて済みそうだし。 「…じゃあ、お送りします」 「助かったわ。さ、すぐにお車、お回しますわ」 そう言って、水城さんは社長室を出て行った。 水城さんが行ってからも、車に乗ってからも、何にも会話は無かった。といっても、速水さんはとても怠そうで眩暈もするらしく、とても会話が弾む状態じゃなかったけど。 ただ一度だけ車の中で「すまなかったな、たまのオフなのに。何か予定があったんじゃないのか…」と気を遣って言っていたけれど、あたしは「いえ、暇ですから…」と答えた。サンダルのことも映画のことも言わなかった。 途中で薬を買っても、会社から速水さんのマンションまでは15分ほどで着いた。エントランスには不思議な形の彫刻があって、なんとなく高級感で気後れしてしまいそうな、そんなマンションだった。あたしも麗と住んでいたアパートから引っ越ししてマンションで一人暮らしをしているけれど、もっとこぢんまりとしたところだ。やっぱり速水さんとは住む世界が違うんだと思う。 車を降りると、あたしは速水さんのアタッシュケースと上着を持って、速水さんがふらつきながら歩く後ろからついて行った。玄関先で帰ろうと思ったけれど、速水さんは本当に辛そうで、最上階まで昇るエレベータの中では壁に体を預けていた状態だったし、玄関に入るとそのままリビングのソファに倒れるように座り込んでしまったので、そのまま放っておけなくて部屋の中まで入ってしまった。 広い、がらんとしたリビングに、座り心地の良さそうな大きな白い革張りのソファと灰皿がひとつぽつんと置かれた白い大理石のテーブル。壁には大きな薄型のテレビがあって、その部屋にあるものはそれだけだった。 「あの、薬を飲んでからベッドで寝た方がいいですよ…。着替えないとスーツが皺になるし…」 「…ああ…、そうだな…」 速水さんは深呼吸をするように大きく息を吐いて、それから寝室に向かった。どうして、そんなに辛くなるまで仕事をするんだろう。女優にとって体調管理は仕事の一部だぞと、偉そうにあたしに言うくせに、自分がこれでどうするんだ。 あたしは、ちょっと迷ってからキッチンに行きコップを探す。大きな造り付けの食器棚の中は、一人分の食器が寂しそうに入っていて、本当にここで一人で暮らしているんだと不思議な気分になる。 ガラスのコップを一つ取り出し蛇口に手を掛けたけれど、ふと冷蔵庫に目を向ける。人の家の冷蔵庫を勝手に開けるのは、少し躊躇う。土足で家に上がってしまうのと同じ気がする。でも、気に入っている水を冷やしているかもしれない。その方が気持ちいいかもしれない。思い切ってドアを開けると、やけに明るい庫内には、やっぱりエビアンのボトルが数本、外国のものらしいライオンのマークのビールが数本、スモークチーズ、冷凍庫には氷がたくさん冷えていた。会社から帰るとお酒を飲んで寝てしまう生活なのかもしれない。 …まあ、あたしの冷蔵庫も、水と缶のカクテルとチョコレートしか冷えてないけど。 コップと冷えたエビアンと薬を持って寝室に行くとドアが細く開いていて、中を覗くと速水さんはすでに着替えを終えてキングサイズの大きなベッドの中にいた。速水さんが小さく見えるベッド。ノックをして部屋に入り、静かに声をかける。 「お薬…持ってきました。起きあがれますか?」 「…ありがとう…。…ん……薬は…飲んだ方がいいんだよな…」 「…そりゃ、当たり前じゃないですか。なに子供みたいな事言っているんですか?ほら、飲んでから寝てください」 「苦手なんだ…。錠剤が喉に詰まるような気がして」 ぷっ…。 …おかしい。 こんなに大人なのに、社長なのに、速水さんなのに、拗ねた子供のようなことを言うなんて。でも。 「あたしも実は苦手です。喉に詰まる感覚がいやで」 あたしが言うと、速水さんはくっくっく…と抑えて笑った。 「チビちゃんと俺とは共通点など無いと思っていたが、思いがけないところで共通点を発見できて嬉しいよ」 もう一度、大きな息を吐いてゆっくり起きあがると、黄色い錠剤を3粒、片目を瞑ってエビアンで一気に飲み込んだ。あたしはそれを固唾を飲んで見守った。 「詰まりませんでした?」 「ああ、成功だった」 真面目に答える速水さんがおかしすぎて、あたしはなんだか愉快になって(熱を出している人の前で不謹慎だけど)、夏用の薄い布団を掛けてあげながら顔が笑ってしまった。 こんなにお腹から笑いが込み上げてくるのは随分久しぶりな気がする。 一度死んでから初めてかもしれない。 速水さんは「ありがとう。少し眠るし、君ももう帰っても大丈夫だ。せっかくの休みに悪かったな…」とひと目で具合が悪いんだと分かる笑顔を見せ、そのまま眠りに入っていった。長い長い睫毛、筋の通った高い鼻。柔らかく乱れる前髪。なんて綺麗な人なんだろう。100年の眠りから姫を覚ましてあげたのは王子様だけど、この王子様は自分が眠りについてしまった。あたしはコップの乗ったトレイを持ったまま、しばらくその場から離れられなくなって佇んでいた。 |
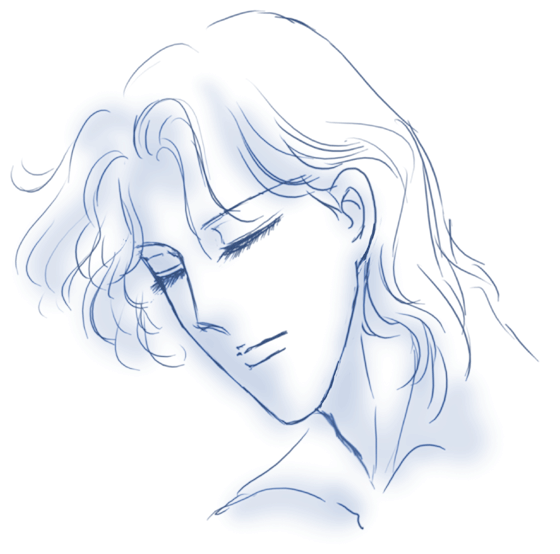
|
一年ぐらい前、あたしは自分で言うのもなんだけど、とても苦しんでいた時期があった。日に日に迫り来るその日を恐る恐る待つしかなかった。だから、その時偶然手にした本に書いてあった方法をどうしようもなく実践することにしたのだ。 いったん死んでから生きる。 その本にはそう書いてあった。悩みと不満を抱えて倒れそうな主人公の女の子が生きていくために実践していた方法だった。 あたしは死んだ。恋する自分は死んだ。そう思うと、おかしなぐらい気が楽になった。…と思った。迎えてしまった結婚式の日も思ったよりも楽に過ごせた。…はず。いったん死んでから、生き返ったのは女優一筋なあたし。 だから、もう平気平気へーき…へーき…。 平気平気と呪文のように思ううちに、そう思うことが習慣になって、例えば何かのパーティで二人が一緒にいるところを見かけたとしても、堪らない笑顔で微笑みかけられたとしても、突然後ろから「チビちゃん」と声を掛けられたとしても、ぜんぜん平気なのだと心が反応する前に頭から指令が出るようになった。 平気、平気。なんにも問題なし。ノープロブレム。 眠り続ける王子様をもう一度だけ眺めて、そうっと寝室を出る。 6月の晴れた日は夏の匂い。 リビングの大きな窓を開けると、広いバルコニーの向こうに青い空が広がる。遠くには霞んだ高層ビル群。灰色の街の所々に緑。揺れる白いカーテン。 時計の針は11時37分。 今から向かえば、間に合う。 いったん死んだ人は、銀座の小さな映画館に行くべきだ。 06.29.2004 |
| fiction menu next |