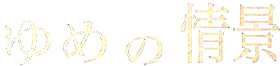
第1話 |
|
幼いの頃の思い出は、広すぎて果てまで行き着くことができないと信じていた屋敷の庭の緑と池に反射するきらきらとした光、お爺様がくださった風船の艶やかな赤、桜色のリボンの付いたお出かけ用の靴。私の笑い声。遠い日のピアノの音色。 まるで水彩画のような淡い優しさの記憶の中の場所。 ピアノを習い始めたのは初等科に上がった頃。屋敷に若いピアノの先生が一週間に一度訪ねてきて、綺麗に切りそろえた桜色の爪と意外なほど小さな手で、バイエルをやっと辿る私の指の形を丁寧に直してくださった。私のレッスンを終えると、先生はにっこり笑い、必ず何か一曲弾いてくださった。曲名はよくわからなかったけれど、どこかで聞いたことのある旋律ばかりで、おそらく私にピアノを音楽を好きになってもらうために弾いてくださっていたのだと思う。ショパンの子犬のワルツをコミカルに弾いてみせたり、モーツァルトのメヌエットをかわいらしく奏でてくださった。 ある日先生が弾いたのは、穏やかな旋律の静かな曲だった。なぜか幼かった私の心に強く何かが響いてきてひどく困った。私にはそれの正体が何なのか分からなかったのだ。胸をざわめかせる静かな旋律。弾き終わってピアノの前に座る先生の傍に立って聞いた。 “せんせい…、これはどんな曲なの?どうしてこんなに胸がいたいの…?” 先生は目を大きく開いて、嬉しそうに笑った。 “紫織ちゃんにも何か感じるところがあったのかしら。これはね、夢を見ているのよ。子供の頃の素直な想いを綴った曲よ。それから、私はもう一つの想いも込めて弾いたの…” “もうひとつ…?” “心の中にずっと住み続けている人を想って…” “…ずぅ…っと…?” “そう。…夢の中で想い続けることは自由ですものね…” “夢は醒めてしまうからつまらない” 私は言う。怖いもの知らずで世間知らずで潔い私が。 “…そっか…。そうね…。夢はいつか醒めてしまうものね。困ったわね” 先生は、私の髪を結んだ白いレースのリボンを軽く触りながら、ただいつものようににっこりとした。先生がどんな想いをその曲に乗せて弾いたのかはわからなかった。 その後、私は体調を崩し長い間入院して退院後もしばらくピアノを触れない状態が続いた。その間に先生はパリに移住した。その頃、私に一通の手紙が届いた。封を開けると、便箋が一枚、それから絵葉書が入っていた。便箋には、恋して止まない人に想いを伝えるために渡仏したのだということと、きちんとピアノを教えてあげることができなかったことへの詫びが小さな女の子へ簡潔に丁寧に書かれていた。恋して止まない人へ想いを伝えるということがどのくらいの喜びと痛みと重さが伴うものなのか、その小さな少女には理解の範囲を超えていた。絵葉書はパリの風景画だった。その水彩の淡い青空に先生の柔らかな文字で、あの時弾いた曲はシューマンのトロイメライでした、と書いてあった。  居間から静かに流れるピアノの音色。トロイメライ。 多忙な夫はたまの休日、決まって夕暮れ時にこれを奏でる。 夫は優しい。いたわってくれる。 その優しさが愛なのかどうかは、もう問わない。ただ、穏やかに日が過ぎていってくれるのならば其れでいい。このまま夫の優しさだけを感じていればいい。 私は決して邪魔はしない。ピアノの指を止めるようなことはしない。 庭に下りて絶望的なほどに紅く染まった西の空を眺めながら、夫のトロイメライを聴く。ゆっくりと静かに流れていく旋律に抗わずに大きく息を吸い、その音を体に取り入れる。それから、胸を締め付ける想いを長い溜息にして夕焼けと共に山の端に沈めよう。 音色が止むと、私は振り返り庭から居間に上がる。 夢想。 夕焼けを映した茜色の居間で夫がピアノの前に座っている。 止んだ音色にまだ心惑わされている。まだ夢の中にいる。 私は一度も夫に訪ねたことは無いけれど、夫が誰を想って奏でているか知っている。夫とこの曲と彼女にどんな繋がりがあるのかは知らないけれど、夫は奏でながら夢の中で彼女と逢っている。彼女への想いの音が穏やかに私に降り注ぐ。 「何を想って弾いていらっしゃるの…?」 そんな馬鹿なことは訪ねない方がいい。どんな答えが出てくるか恐くて仕方ないのに。それでも、私は確かめたい。 “君を想って…” そうおっしゃるはずがないことは承知している。 “何も…” せめて、そう答えてくださることを確かめたい。 けれど、夫は困ったように顔を歪ませる。歪んだ笑顔を私に返す。言葉もなく。困ってしまうのは私の方なのに…。 そう。困ったことに、私はその眉を寄せた笑顔を愛している。 恐ろしいほどに美しい涼やかな目を。口の端をほんの少しだけ上げた笑顔を。いつか彼女の前でみせていた屈託のない笑顔を私に向けてくださることが永遠に無いのならば、私はこの静かに歪んだ笑顔を愛そう。そして、夫の裏切りの音色を、私に差し出される夫の想いの全てを愛そう。 「愛しておりますわ…」 夫の肩に触れる。 目蓋を伏せ自分の肩に置かれた私の指先を見ると、また何事も無いように視線を戻す。 憐れなこと…。 夫はご存じ無いのだ。夫の愛して止まない彼女が、紛れもなく夫を愛していることを。愛し合っている二人を無情にも引き裂いているのは私。そんな単純な構図を理解していないわけではなく、この構図が二人を苦しめていることを知らないわけではなく、ただ、私は夫を愛している。 だから私は祈る。年若い彼女が一刻も早く他の誰かを愛し始めることを。いつかあのピアノの先生のように、トロイメライの音色とともに夫が真実の愛を告げるため彼女に会いに行く前に。 ただひたすら… 祈っている… 10.13.2004 |
| fiction menu next |