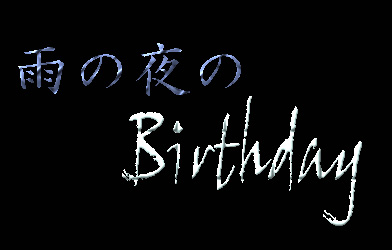 written by 咲蘭 . 夜になると酷い雨が降りだして、真澄は軽く舌打ちをして社長室の窓に次々に打ち付ける水滴の群れを睨んだ。べつに、特別に何かが起こることを期待しているわけではないが、それにしても自分の誕生日に冷たい雨では、ますます気分が憂鬱になるというものだ。 真澄は適当なところで仕事に区切りをつけると、いまだにパソコンに向かっている水城に声を掛け、地下の駐車場に向かう。水城が何か言いたげな眼差しをよこしたが、どうせ水城の考えていることなどわかっていると真澄は思う。「いつまでこの状態を続けるおつもりですの?」といったところか。 BMWのエンジンを掛けて、地上へ登る坂を一気に走らせる。地上に出た途端に、フロントガラスを水滴が襲い、急ぎワイパーを作動させる。そこで、真澄が息を飲む。 「まさか…!?」 BMWのライトが映し出したのは、大都芸能ビルのエントランス付近で、傘も差さずに雨に打ち付けられている人影。黒髪で、小柄な女性。見間違えるはずもない人。 真澄は急ブレーキで歩道に寄せて停車させると、低い植栽を軽々と超えて走り出す。 「チビちゃんっ!!」 雨の音と交じった真澄の叫び声に、その人影が鋭く振り向いて、そして、固まった。 「…速水さん」 「このバカ娘っ!来いっ!!」 真澄はマヤの腕を乱暴に掴んで、引きずるようにBMWに連れて行く。意外にもマヤはこれといった抵抗も見せず、腕を掴んで歩く真澄に、黙ってついていく。真澄もまた黙ったまま助手席のドアを開けて、マヤを放り込んだ。 トランクを開け、かろうじで入っていた一枚のタオルを持って運転席に戻る。マヤは、助手席で黒髪から水滴を落としながら、俯いていた。 「これで髪を拭きなさい。このままでは風邪を引いてしまう」 マヤは僅かに頭を動かして真澄を見て、少し逡巡してから、真澄の差し出すタオルを受け取った。真澄は、暖房を最大に入れて濡れたジャケットを脱ぎ、シートに体を預ける。 「…いつから、あそこにいたんだ?なぜ、あそこにいた?誰に用だったんだ?」 一度疑問を口に出すと、次々にそれに連なって疑問が湧いてくる。マヤは髪の毛を拭う手を、ぎゅっと握った。 「…あたしが来たときは、まだ雨が降ってなくて、中に入ろうか迷っているうちに降りだしてきたんです」 雨に気付いたときには、すでに7時ぐらいだったか。真澄は腕時計をちらりと見て溜息をつく。 「もう9時を過ぎてる。チビちゃん、きみはあんな場所に何時間も雨に打たれて立っていたというのか?いったいなにがあった?」 マヤが傘も差さずに雨に打たれることは、もう珍しくもない。 「…驚かせて、すみません」 「いや、たいして驚いてない。君が雨に打たれているところは、もう見慣れた。いったいこれで何度目だと思う?まさか、また紅天女の役作りとでも言うつもりじゃないだろうな?」 暖房の風が、ごうごうと音を立てて吹き付けてくる。マヤの髪が乾きかけて、風に煽られているのが見えた。マヤは、口角の端をきつく結んで、じっと座っている。どうやら真澄の問いには何も答える気は無いらしい。真澄は小さく苦笑して、右のウィンカーを光らせると夜の街を走り出す。 「きみのアパートまで送ればいいのか?」 ワイパーが忙しなく雨粒を掻き分けるけれど、雨の夜は視界が酷く悪い。真澄の問いにマヤからの返事はない。 「まったく、強情だな。きみが考えていることはよくわからん。このまま、行くあても無く彷徨えとでも?」 それも悪くないと真澄は内心思う。マヤと二人、このままどこまでも行けたらいいのにと。それができたらどんなにいいだろう。現実逃避でもかまわない。 試演後に迫っている紫織との結婚から逃避して、マヤと二人でどこまでも彷徨う。ありえない、都合のいいだけの想いだ。 「とにかくその格好じゃ風邪をひいてしまう。アパートでいいな?」 真澄は、ふっ…と息を吐くと、脳内を支配しそうになった甘美な想いを打ち消すように、ハンドルを左に切る。 「いやっ!」 「えっ!?」 「あのっ、アパートじゃなくていいんです!どこでもいいんですっ!速水さんを待ってたんです、あたし、大都芸能の前で」 「…俺を?」 タオルを握り締めて、俯くマヤの耳が心なしか赤い。 「チビちゃんらしくもない。俺に用があるのなら、社長室に乗り込んでくればいいじゃないか」 冷静を装って言ってみるものの、真澄は動揺を隠しきれていないのではないかと思う。マヤが自分を待っていた。しかも何時間も、雨に打たれながら。 「…行こうと思ってました。でも、行けなかったんです」 「ますます、きみらしくもない。豆台風の勢力が低下したか」 「…豆台風なんて、なんにも気付いていなかったから、だから、できたことだったんです。もう、あんなふうにはなれない…です」 前方の信号が赤に変わり、真澄は車を停車させる。隣には、乾ききっていない黒髪を弄るマヤ。ワンピースがしっとりと濡れ、まだ少女だと思っていたはずのマヤの体の線を美しく見せているから、真澄は慌てて視線を逸らす。艶やかな女性へと変貌を遂げていくマヤ。大人になる日を待っていたはずだったのに、今はそれは少し辛く感じられる。 マヤの前で自分を保つことは難しい。いつだって頑丈に鍵を掛けているはずの生身の感情を、いともやすやすと露にしてしまう。信号が青に変わり、再び雨で滲んだ夜の光が、次々と後方に流れていく。 「それで、…俺にどんな用があったんだ?」 マヤの話は核心に触れるまで、忍耐強く慎重に聞いていかなければいけない。どんな用でもいいと思った。いつもの豆台風のような、酷い罵りでも構わないと思った。 「…速水さん、今日は速水さんの誕生日ですよね…?」 「ああ、そのようだな」 「まあ、その、おめでとうの一つも言ってみようかと…」 「…意外なことを」 あまりにも突拍子も無い切り口から入るから、マヤの話しの道筋がまるで見えない。おめでとうを言いに来て、数時間も雨に打たれる必要がどこにあるというのだろう。 「紫織さん…と、一緒にいないから、驚きました…」 「誕生日にいつも通り仕事をしていちゃおかしいか?」 「おかしくないです…けど…」 そこで会話が途切れてしまい、車内には微妙な沈黙が落ちる。もちろん紫織から食事の誘いはあったけれど、自分の誕生日まで、紫織と一緒に過ごすのはきつい冗談のように思えた。よほど、スケジュールの都合で延び延びになっていた食わせ者として有名な四ツ星銀行頭取の接待の方ほうがましだと、わざわざ予定を入れ紫織には断りの連絡を入れたが、先方の都合で接待は直前キャンセルとなったのだった。紫織には、それがキャンセルになったことは伝えていない。 今、自分の隣の助手席に座っているのが紫織ではなく、マヤであることが奇跡のように思えた。 「…紅天女は、どうだ?試演まではあとわずかだが」 沈黙に耐えられず、共通の話題に触れてみると、マヤも沈黙が辛かったのか、ふと和らいだ笑顔を見せた。 「必死です。夢に向かって一歩一歩進むために、毎日、戦いを挑むように稽古してます」 「そうか。チビちゃんらしいな」 「観てほしいと思っていますから。紫のバラの人にあたしが紅天女になった姿を。誰よりも」 「…そうか。紫のバラの人も、そこまで想われて幸せなことだな」 誰よりも、マヤに紅天女になってほしいと願っている。速水真澄として。そう言葉にできたらどんなに幸せなのだろう。 「…速水さん」 「なんだ」 「紫のバラの人は、観てくれますよね?試演を観に来てくれますよね?」 ワイパーが往復するフロントガラスの向こうの雨の夜を睨む真澄に、マヤの強い視線が突き刺さる。紫のバラの人は、観てくれますよね?紫のバラの人は。 「…なぜ、俺に訊く?」 ぽつりと呟かれる真澄の低音の声。紫のバラの人に嫉妬したのかもしれなかった。愚かなことだ。自分が作り出した偶像に嫉妬するなど、これ以上の愚か者はいないのに。 マヤの瞳が一度大きく見開かれて、それから歪んだように寂しげに笑った。 「速水さんなら、なんでも知ってそうだと思ったから…。いいんです。適当に、たぶんなって答えてくれたら、それで満足ですから」 抱き締めてしまいたくなった。運転中でなければ、もしかしたら抱き締めてしまっていたかもしれなかった。 「…そんな言葉で満足なのか?」 「だって、贅沢を言い出したら歯止めが利かなくなっちゃいます。紫のバラの人にとって、あたしは女優として最高の存在でいたいって、それだけにしておかないと、もう…」 「マヤ…?」 いったいマヤは紫のバラの人に対して、どんな贅沢を望んでいるというのか。マヤはいままで、たった一度も何かが欲しいと紫のバラの人に伝えてきたことは無かった。ただ、紫のバラの人の勝手な好意を、感謝とともに受け取り、女優として輝くことが恩返しになるからとがんばってきたはずだった。 そのマヤがここまで抱いているという願いだからこそ、どんな願いでもすべて叶えてあげたいと思うのに、たった一言、そんな言葉すら口に出すことができない。 マヤのアパートまでは、あとわずか。助手席でタオルをぎゅっと握り締めて小さく座るマヤを、このまま帰してしまうのは、どうしても忍びなかった。 「チビちゃん。きみが紫のバラの人に抱いている願いを、今夜、ひとつだけ俺が叶えてやりたい。きみにとっては迷惑な話だろうが、あいにく今日は俺の誕生日でね、俺への誕生日プレゼントだと思って、この戯言に付き合ってくれないか?」 「…ざれ言って…。速水さん、どうしてそんなことを…?」 目を丸くしたマヤの顔が、あまりにも可愛らしく思えて、真澄は思わず笑みをこぼす。きっとまたおかしなことを企んでいるとでも思っているのだろう、この可愛い人は。 「…気まぐれだ」 おかしな論理だと自分でも思うが、それ以外に思いつかなかった。ただ、もう少しマヤと一緒にいたかった。マヤの願いをひとつでもいい、速水真澄として叶えてあげたかった。 この小さな交差点を左折すればマヤのアパートに到着する。 「とはいえ、そのままでは風邪をひいてしまうな。一度、部屋に戻って着替えてくるといい」 路地に入った先に立つアパートの前で停車する。ワイパーだけが、忙しなく動き続ける。リズミカルなワイパーの音。車体を叩く雨粒の音。マヤは車を降りようとしない。 「チビちゃん、どうした?」 「…このままで大丈夫です。もう、だいぶ渇いてきたし。それに、車を降りてしまうと、せっかくの勇気が消えてしまいそうな気がするから…」 「勇気…?」 マヤは真澄にしっかりと視線を向けて、ごくりと唾を飲み込んだ。 「速水さん。ひとつだけ願いを叶えてくれるんですよね。紫のバラの人への願いを、たったひとつだけ…」 「ああ、俺に出来る範囲のもので頼むよ」 「できます…。速水さんだもの…」 「マヤ?」 「速水さんに、言ってほしい台詞があります」 「台詞?バラに添えられたメッセージカードに書いてあるような?」 「…いえ」 マヤの真剣なまなざしは、戯言に付き合っているだけのようには見えない。真澄は何か後ろめたい気分になり、とてもマヤと視線を合わせられずに、ハンドルに触れた自分の指先を見つめた。とんとんとハンドルを弾く人差し指。ワイパーと雨音の入り混じった不協和音。マヤの唇が動いた。 「…速水さん。おれが紫のバラの人だっ…て、たった一言でいいから、言ってくれませんか」 その瞬間、すべての雑音が消えたと思った。 人差し指の動きも止まった。 真澄は、ゆっくりと首だけを回して、助手席を見遣る。 そこにあるのは、マヤの強い、憧れてやまない熱いまなざし。 「マヤ…。それがきみの願いなのか?俺がその台詞を言うことに、意味はあるのか…?」 「…それだけを言ってもらえたら、あたし、ちゃんと自分の気持ちを伝えられるような気がするんです…」 “自分の気持ち”をいったい“誰に”伝えようというのか、マヤの考えていることは、まるでわからなかったが、その台詞をマヤに対して言うことは、抗いがたい誘惑だった。それが、たとえマヤの想う架空の人物の代理だとしても。 真澄は、目を瞑って、浅く息を吐いて、ゆっくりとまぶたを開ける。 「…俺が」 もう一度、浅く息を吐く。 「紫のバラの人だ」 自分の声であって、自分の声ではないような気がした。 マヤの大きな瞳の奥で光が揺れて、涙が浮かんで、一粒の滴になる。 「俺が、紫のバラの人だ」 ずっと心に秘めていて、ずっと言えるはずもなくて、 それでも、ずっと言いたかった台詞。 言いながら、またひとつマヤによって頑丈な鍵が外れていくのを感じる。一度口に出してしまえば、マヤが気まぐれだと戯言だと思っているとしても、そこに真実を込めて言うことができる。俺が、紫のバラの人だ。 マヤの頬を涙の滴が幾筋も流れる。唇を噛んだその奥からは嗚咽が漏れ、ついに、大きく息を吸って泣き出した。どうして、そんなに涙を流すのだろうと思った瞬間、マヤが運転席の真澄に腕を伸ばして抱きついた。 「その言葉が聞けて嬉しい…紫のバラの人…。その言葉をずっとずっと待っていました」 これが現実だとしても、現実感を伴うことのない応酬。それは、気まぐれな戯言のうえでしか成り立たない会話。その酔いにも似た浮遊感に、言うはずもなかった言葉までが零れ出る。 「きみが嬉しいと思ってくれるなら、俺はそれの何倍も嬉しい。きみが紅天女になることを誰よりも願っている。もう何年もきみだけを見てきた」 マヤが、抱き付いていた真澄の胸から、そっと真澄の瞳を見上げる。ひとつ鍵が外れた今ならば、いつもよりも素直に想いを伝えられそうな気がした。紫のバラの人という、仮面を被った今ならば。 「きみへの憧れをバラに託した。泣いているきみを抱き締めるかわりにバラを贈った。つねに前を向いて歩くきみへの励ましになればとプレゼントを贈った」 マヤの瞬きもせずに揺れる瞳。なんだと思ってこの告白を聞いていることだろう。困惑か失望か。滑稽だとでも思っているのかもしれない。 「速水さんの言葉には、ほんの少しでも真実がありますか…?」 すべてが真実だ。一滴の嘘も滲んではいない。マヤの背中に腕をまわし、黒髪の隙間から見える耳元に、小さく囁く。華奢なくせに熱い情熱を秘めたマヤ。 「きみが悲しいのなら、気まぐれな戯言だと思えばいい。そうして忘れてしまえばいい」 真澄の背中のワイシャツを掴んだマヤが、首を何度も横に振って叫ぶ。 「ううん、悲しくなんかない!速水さん、あたし、その言葉に真実があると思いたい!…思っていたいんです!」 「…マヤ?」 「どんなときでもあたしを見守ってくれていたのは、速水さんだった。嫌味な社長のふりして、本当は、紫のバラの人として、あたしをずっと。ずっと感謝の気持ちを伝えたかった…」 この衝撃をどう言い表したらいいのだろう。世界がひっくり返るという表現は、こういうときに使うのだろうか。マヤが、自分が紫のバラを贈っていたことを知っていたなんて…。 ずっと、速水真澄と紫のバラの人が同一人物だと知れば、マヤが酷く悲しむだろうと思っていた。あんなにも憎んでいる男が、感謝すべき人だと知ったら、ショックを受けてしまうだろうと。だからこそ、それが怖くて告白できなかったというのに。 完敗だった。この子には、きっと一生勝てやしない。 「…マヤ。俺のきみへの想いの象徴が、紫のバラだった。女優としてのきみだけではなく…、マヤ自身への想いだと思ってくれていい。すべて、俺の真実だ」 伏し目がちに優しくマヤを見つめて言うと、腕の中でマヤが小さく震えた。俯いて、頼りなく。その離れがたい温もりを抱き締める。 「…あたしは、もう、その言葉だけで思う存分紅天女になれる。もう絶対に迷いません。速水さんが、別の誰かと結婚しちゃっても、あたし、この言葉、一生忘れない…」 マヤが真澄の胸からそっと離れる。あるべき存在が、消えてしまうような虚しさで、胸が痛くなる。 「…抱き締めてくれて、速水さんの気持ちを聞かせてくれて、ありがとうございました…。今日、思い切って大都芸能まで行ってよかったです。もう、思い残すことは…無い…です」 ありがとうございますと言いながら、悲しげな笑顔でマヤは助手席のドアに手を掛ける。ドアを開けてしまえば、今、二人の間に確かにあった空気が雨に溶けて跡形もなくなってしまうような気がした。 「待てっ!」 ドアに触れたマヤの右手を、真澄の大きな手が掴む。覆いかぶさる真澄の重み。触れ合うほどに近づく唇。頭のどこかに、雨の音が絶え間なく聴こえてくる。 「…だめです。これ以上ここにいたら、あたし、言っちゃいけないことまで言ってしまいそうになるから…。求めちゃいけないものまで欲しがってしまうから…」 「行くな、マヤ。欲しがればいい。マヤの気持ちを素直に口にしたらいい」 お互いの鼓動まで感応しあっているかのようだった。今聞かなければ、一生聞けないような気がした。マヤの真実。マヤの本心。 「……速水さんが…好き。ごめんなさい…好きなんです…」 ただ夢中でマヤを抱き締めた。望んではいけない言葉だと思っていたのに。ありえないことだと、ずっと思ってきたのに。マヤからの夢のような告白を、謝りながら言わせてしまった自分の不甲斐なさを痛いほど感じる。 「謝らないでくれ。俺がいま、どれほどの幸せを感じているか、きみにわかるか?謝るのは俺のほうだ。マヤが素直に、幸せな気持ちで、もう一度好きだと言ってくれるようになってみせる…」 「…速水さん…?」 腕を緩めて、マヤの瞳を真っ直ぐに見る。この小さな体にどれほどの情熱を秘めて、どれほどの悲しみを抱えてきたのだろう。もう迷わずに、マヤへの想いを封じ込めることなく、生きてみようと真澄は思う。 「きみは紅天女を目指すんだ。長年の夢が、もうすぐ手に届きそうなところまで来ている。迷わずに、きみだけの紅天女になってほしい」 「はい…」 「俺も、必ずマヤの紅天女を観る。きみの紅天女を観ることが、俺の長年の夢だったんだ。そのときには、きっと迷いの無い道筋をつけて、正々堂々と紫のバラをマヤに贈りたい」 小さく何度も頷くマヤの瞳から、涙のつぶが溢れ出る。真澄はマヤの黒髪を何度も撫でて、その涙に口づけをする。 「今日は、これまでの人生最高の誕生日だ」 冷たかった秋の雨は、柔らかな雨音に変わり、まるで二人を包み込むように優しく降り続く。 一年に一度、訪れる誕生日。 けれど、この雨の夜の誕生日のことは、一生忘れない。 秘めた想いが溢れた夜。 想いが通じた夜。 迷いを捨てた誕生日。 11.03.2006 誕生日を絡めてみました。(そして、サイトテーマには絡んでません(大汗)) マヤのアパートの前に停車した車内でのできごと。アパートの窓から麗が、やや呆れながら見ててくれても楽しいなと、想像しつつ書きました。 マヤマスパロの肝のひとつとして、どんなシチュで、どんな言葉で告白させようか、というのがあると思うのですが、どうやら、「雨」「夜」「車内」というのは、私の好きなシチュらしい…ということが良くわかって苦笑いでした。ハハハ。バリエーションは無いのか? というわけで、若干詰め込み警報の鳴り響くヘタレ短編となり、ごめんなさいですが、マヤマスの未来に幸せを!という気持ちだけは、たっぷりと込めました。ひとまずこれでお祝いさせてください。 社長!!お誕生日おめでとうございます!! |
|
close |